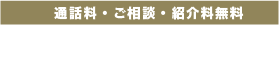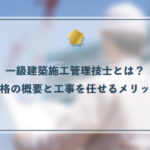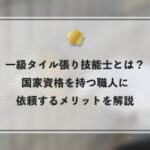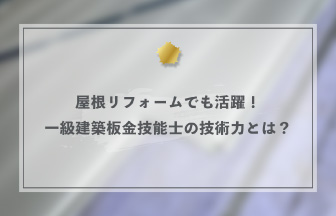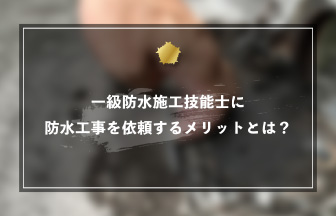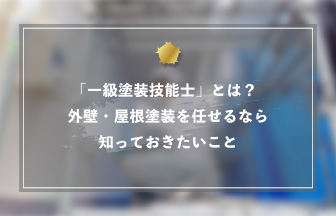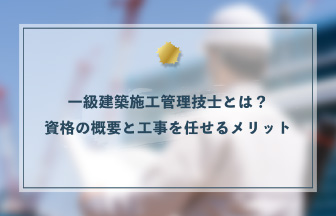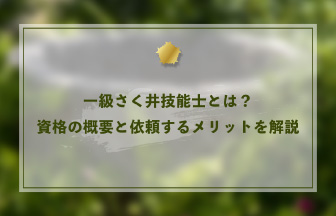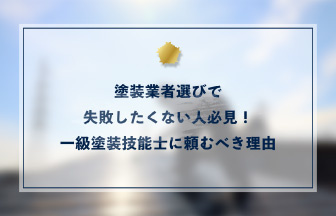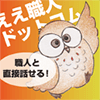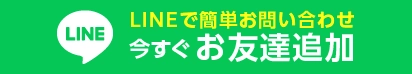電気工事に関わる工事現場では、「誰が工事を管理するか」によって、仕上がりの安全性・品質・効率性が大きく変わります。特に、公共施設や商業ビル、高層マンションなど大規模工事では、国家資格である「一級電気工事施工管理技士」が在籍しているかどうかが、業者選びの大きな判断材料となります。
この記事では、「一級電気工事施工管理技士」の資格概要や業務内容、依頼するメリット、そして優良な電気工事業者を選ぶ際のポイントまで詳しく解説します。
一級電気工事施工管理技士とは?

国家資格としての位置づけ
「一級電気工事施工管理技士」は、国土交通省が管轄する国家資格で、建設業法に基づいて制定されています。建築工事の中でも、電気設備工事(照明・配電・受変電設備・情報通信設備など)の施工計画や現場管理を行うために必要な資格です。
この資格を取得すると、「監理技術者」として特定建設業者の電気工事に従事できるようになり、元請業者として大規模な電気工事を受注することが可能になります。
一級電気工事施工管理技士の業務内容
現場全体の電気工事を統括管理
一級電気工事施工管理技士の主な業務は以下の通りです。
- 施工計画の作成:資材手配・工程管理のスケジュールを立案
- 工程管理:工期内に作業が終了するよう進捗を管理
- 品質管理:電気設備の仕様通りの品質を確保
- 安全管理:感電・火災・高所作業などのリスク管理
- コスト管理:予算内で施工できるよう資材や人員を調整
- 協力業者との連携:電気・通信・空調など複数の業者との調整
施工管理技士は「現場監督」というより「現場のプロデューサー」に近い存在で、建物のインフラ中枢を担う電気工事の要です。
試験概要と合格率
一級電気工事施工管理技士になるには、以下のステップを踏む必要があります。
1. 受験資格
受験には学歴・資格・実務経験に応じた条件があります。代表的な例は以下の通りです。
- 大学(指定学科)卒業:卒業後 3年以上 の電気工事に関する実務経験
- 高専・短大(指定学科)卒業:卒業後 5年以上
- 高校(指定学科)卒業:卒業後 10年以上
- 指定外学科卒業:さらに長い実務経験(例:高校は11年6か月以上)が必要
また、第一種電気工事士や電気主任技術者などの資格を保有している場合、実務経験が短縮・免除される特例もあります。
2. 年齢要件(第一次検定)
- 試験実施年度に満19歳以上 であること(例:令和7年度に申請する場合、生年月日が平成19年4月1日以前であること)
3. 制度改正と経過措置(第二次検定)
令和6年度から、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。
ただし、令和10年度までの間は経過措置として 旧受検資格 でも第二次検定を受験できます。
経過措置のポイント
- 令和6〜10年度の間に「旧受検資格」で第二次検定を受験した人は、令和11年度以降も継続して再受験が可能(欠席者を含む。ただし辞退者は除く)。
- これにより、従来の実務経験年数に基づいて受験できる猶予期間が設けられています。
4. 試験内容
- 第一次検定(学科試験)施工管理法、法規、電気設備に関する知識を中心に出題。マークシート方式で、基礎知識から応用的な内容まで幅広く問われます。
- 第二次検定(実地試験)現場での経験や応用力を記述式で評価。施工計画、課題解決の手法、現場対応力が問われます。
5. 合格率(過去実績)
- 第一次検定: 約40%前後
- 第二次検定: 約50〜60%
第一次検定の方が合格率は低く、学科の壁を突破できるかどうかが大きな関門となります。
一級電気工事施工管理技士に依頼するメリット

電気工事は、住宅やオフィスビル、公共施設など建築物の「生命線」ともいえる重要な部分を担っています。照明・配線・受変電設備・防災システム・通信インフラといった機能は、すべて正しい設計と確実な施工があって初めて安全に利用できます。そんな重要な工事を任せるなら、国が認めた専門資格である一級電気工事施工管理技士の存在は大きな安心材料です。
ここでは、資格者が関わることによる具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
高品質な施工が期待できる
一級電気工事施工管理技士は、電気設備に関する深い知識と実務経験を備えており、設計図通りかつ法令基準に適合した施工を行うことができます。
電気工事は配線や機器の多くが壁や天井の中に隠れてしまうため、工事完了後に利用者の目で確認することは困難です。だからこそ、施工不良があると「気付かないまま使い続ける」リスクが生じ、最悪の場合は火災・感電・漏電事故につながります。
資格保有者が管理に携わる現場では、材料選定から接続方法まで安全基準を満たした施工が徹底され、見えない部分にまで技術力が反映されるため、長期的に安心して使用できる建物になります。
大規模工事・公共工事に対応できる
建設業法では、4,500万円(建築一式工事では6,000万円)以上の電気工事には監理技術者の専任配置が義務付けられています。そして、この監理技術者として登録できるのが、一級電気工事施工管理技士です。
つまり、一級資格者がいなければ、大規模工事や公共施設の工事を受注すること自体ができないのです。学校や病院、庁舎、工場、ショッピングモールなど、大勢の人が利用する建物においては、電気設備の信頼性が社会的に求められます。そのため、資格者が関与していることは、そのまま工事の安全性と信頼性の証明にもなります。
工期の遅延リスクを最小限に抑えられる
大規模な電気工事現場では、電気工事単体だけでなく、建築・設備・通信など多職種の工程が複雑に絡み合います。もしスケジュール管理が甘ければ、資材不足や作業員の待機時間が発生し、工期の遅延やコストの増加を招きます。
一級電気工事施工管理技士は、全体の工程を見渡して必要な資材や人員を最適に配置するスキルを持っています。例えば、配線工事と空調ダクト工事が同じ天井スペースで重なる場合、作業順序や時間配分を調整することで、無駄なく効率的に工事を進めることができます。結果として、納期遅延を回避し、コスト増大のリスクも防げるのです。
万が一のトラブルにも冷静に対処
建設現場では予想外のトラブルがつきものです。電気機器の不具合、資材の納期遅れ、突発的な停電や天候による作業中断など、あらゆる事態が発生し得ます。
その際、現場に経験豊富な一級施工管理技士がいれば、迅速に原因を突き止め、代替案を示し、関係者に説明したうえで工事を続行することが可能です。特に施主や管理会社にとっては、「トラブル時にどう説明・対応してくれるか」が業者選びの重要な基準となります。資格者は現場対応力と説明責任を果たす能力を備えているため、施主にとって大きな安心感となります。
資格保有者が在籍する業者の選び方

一級電気工事施工管理技士がいるといっても、資格の「名義貸し」や、現場に実際に関与しないケースも残念ながら存在します。依頼先を選ぶ際は、以下のような点を確認することが大切です。
一級資格者が現場に関与しているか
単に「在籍している」だけでなく、実際に施工計画や監督業務に携わっているかどうかを確認しましょう。名義貸しだけの業者は避けるべきです。
施工実績を提示しているか
過去に類似した規模や用途の電気工事を行っているかどうかを確認することで、安心度が高まります。写真や具体的な事例を提示できる業者は信頼性が高いといえます。
見積書に明確な内訳があるか
「工事一式」などの曖昧な表記ではなく、材料費・人件費・管理費・保証費といった項目が細かく記載されているかを必ず確認してください。
保証内容やアフターサービスの有無
電気設備は工事後に不具合が出ることもあるため、保証期間や定期点検、緊急時対応の体制が整っているかをチェックしましょう。
どんな工事に必要とされる?(一例)
一級電気工事施工管理技士が活躍する現場例
- 官公庁の庁舎・学校・病院の電気設備工事
- 大規模マンションの受変電設備工事
- ショッピングモールやオフィスビルの照明・配線工事
- 高速道路・鉄道施設の電力供給システム
- 工場の動力配線や制御設備の施工管理
まとめ
電気工事の質は、実際に工具を握る職人の腕だけでなく、現場を管理する人間の力量によって大きく左右されます。特に、大規模工事や特殊設備が関わる現場では、「一級電気工事施工管理技士」が関与していることが、高い安全性・信頼性・施工品質を確保するための重要な要素になります。
電気工事を依頼する際には、ぜひ資格保有者の有無だけでなく、実際に施工に関与するか・過去の実績があるかを確認しましょう。